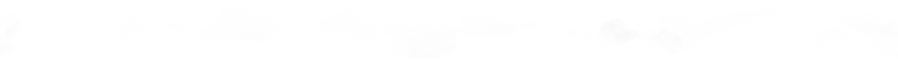南部エチオピアの少数民族
オモ川下流域に位置するマゴ国立公園の周辺には、アリ、ムルシ、カロ、バンナ、ハマル、ダサネチといった比較的人口の少ない民族集団が居住し、人類初期の要素をとどめる独特の文化を残しています。これらの少数民族の中でも特に有名なのがムルシ族で、女性が下唇を切って、土器や木製の皿をはめる風習で知られています。周辺の民族集団は、国立公園設立以前から公園領域内で養蜂を行っていました。国立公園が設立され、境界内での人的活動が全て禁止された後も、養蜂は一定の手続きをすれば許可されており、園内には1万ともいわれる養蜂箱が設置されています。
ジンカとマゴ国立公園周辺の少数民族
ジンカ(Jinka)は、アルバミンチから車で2時間~2時間半程度の距離にあります。エチオピア南部のオモ川下流域に位置し、多くの少数民族の文化や生活様式が見られる地域の中心地であり、周辺地域の探索や、マゴ国立公園(Mago National Park)やオモ国立公園(Omo National Park)へのアクセスの起点となっています。エチオピア南部では、さまざまな民族が集まる定期市が毎日開催されています。例えば、ハマル族、バンナ族、カロ族の人々が集まるディメカ(Dimeka)の土曜市やトゥルミ(Turmi)の月曜市、カイアファール(Key Afar)の木曜市、そしてコンソ族が集まる月曜市などが特に有名です。これらの市では、日用品から水入れの壺、香辛料、フルーツ、穀物などの食料品、そして女性が髪に塗る赤土など、市によって取り扱われる商品は多岐にわたります。
ムルシ族 / Mursi
ムルシ族はマゴ国立公園内に居住し、女性は「デヴィニャ」と呼ばれる唇装飾(リッププレート)を身につけます。デヴィニャは美しさを象徴し、結婚時の牛の数に関連しています。また、収穫が終わる8月から9月には「ドンガの儀式」と呼ばれる戦いが行われ、2m以上の杖を使った競技や模擬戦闘が行われます。
カロ族 / Karo
カロ族の居住地域は、南部オモ川流域にあります。美的な要素を重視した文化で知られており、特徴的なボディペイントや装飾品を身につけています。特に男性は白い粘土を使って顔や体に装飾的な模様を描いています。また、カロ族は水辺での漁労や灌漑農業を行い、オモ川を通じて他の民族と文化的な交流や貿易を行っています。オモ川を見下ろす高台にあるコルチョ村やダス村などは有名です。
バンナ族 / Banna
バンナ族の居住地域はオモ川周辺に広がっており、カイアファール(Key Afar)を中心に、ジンカやトゥルミの周辺にまで及びます。バンナ族は独特の装飾や身体装飾を好み、特に女性はビーズや色とりどりの布で作られたネックレス、ブレスレット、頭飾りなどを身に着けます。
ハマル族 / Hamar
ハマル族はトゥルミ近郊に住み、女性は豪華な髪飾りや装飾品を身につけ、特に女性は髪や体に赤土を塗り、装飾的なスカーフやビーズで作られた首飾りを身に着けます。男性には「ブルジャンピング(牛跳び)」と呼ばれる伝統的な成人儀式があります。若者が成人を迎える際に行われるもので、牛の背中に飛び乗ることを試みる勇気と力強さを示す儀式です。
コンソ族 / Konso
コンソ族は約20万人の人口を抱える民族で、彼らの町コンソ(Konso)を中心に暮らしています。毎週月曜日には大規模な市場が開かれます。彼らはエチオピア最大の民族グループのオロモ族に近い関係にあり、約500年前に遊牧民との争いによりサバンナ地帯から追われ、山の頂上に移住したと言われています。彼らはエチオピア正教を信仰し、先祖崇拝も根強く残っており、現在も王が存在し、観光客は王宮を訪れることができます。かつてはコンソの英雄が亡くなると、「ワカ」と呼ばれる墓のようなものを建てて祀っていました。しかし、古いワカの多くは観光客や研究者によって持ち去られ、現在ではわずかに王宮の近くに残るのみとなっています。