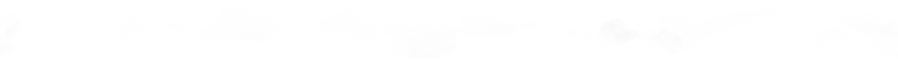イスタンブール
/ Istanbul
ボスポラス海峡を隔てて、アジアとヨーロッパにまたがるトルコ最大の都市。ボスポラス大橋とファーティフ・スルタン・メフメット大橋によって結ばれています。歴史は長く1600年(その間に122人の権力者が手にした)に渡り、ローマ帝国、ビザンチン帝国、オスマン帝国の首都でした。そのため旧市街は歴史地区として、世界遺産に登録されています。ビザンツ帝国時代は、コンスタンチィノープルと呼ばれ、シルクロードの終着点として繁栄の極みにあり、長安に並ぶ世界最大の都市のひとつでした。現在の首都はアンカラですが、イスタンブールの人口はアンカラを上回り、現在でも文化、経済の中心です。開発も進んでいますが、長い歴史を刻んできた街には見所がつきません。
トプカプ宮殿/Topkapı Sarayı
ボスポラス海峡、金角湾とアルマラ海の3方を海に囲まれた丘の上に建っています。外壁内の総面積は約700,000m2あるといいます。15世紀後半に建築が始まり19世紀にかけてオスマン帝国の中心として君主たちが暮らした宮殿です。敷地内には、様々な建物が迷路のようにつながており、内装や宝物は豪奢を極めていますが、全般的に地味な印象を受けるかもしれません。それはオスマン帝国が、遊牧民の国家であり、屋外の自然との関わりを重要視していたからだとも言われています。
アヤソフィア/Ayasofya Camii
ビザンツ建築の最高傑作と言われ、4世紀後半ローマ帝国のコンスタンチヌス1世によって建てられ、6世紀にユスチニアヌス帝によって再建されました。ビザンチン帝国時代には、ギリシア正教の総本山でしたが15世紀オスマン帝国に征服されるとモスクに造り返られ、トルコ共和国誕生後に博物館として一般に開放されるようになりました。中には、キリストのモザイク画が漆喰で塗り固められていた様子が見学でき、外にはモスクを感じるミナレットが建っています。宗教の変遷に翻弄されてきた姿が確認できるでしょう。
ブルーモスク/Sultanahmet Camii
正式名称を「スルタンアフメット・ジャーミィ」といいますが、モスク内部の壁が美しい青と白のイズニックタイルで飾られているため「ブルーモスク」の愛称で親しまれています。世界でも珍しい6本のミナレット(尖塔)を持つモスクです。その由来は設計時に「アルトゥン=黄金」を「アルトゥ=6」と勘違いしたためとも言われています。1609年に建築家のアフメットにより建てられました。トルコのジャーミィはミナレットのほかに、丸天井とドームに特徴がありますが、ブルーモスクも大ドームと4つ副ドーム、30の小ドームを持つ荘厳な寺院です。